そうなると、広告などで目にすることが多くなるのが、
「お中元」の文字。
これまでは気にもしなかったという人も、
「就職した」「結婚した」など、新生活を始めたことで
今年初めてお中元を準備するという人も、実は多いのでは?
でも、初めてのお中元だからこそ、なにが正しいマナーなのが、
どんな送り状や礼状が必要なのか、わからないですよね?
そこで、初めてのお中元だからこそ知っておきたい
お中元の話をまとめてみました。
スポンサーリンク
目次
お中元の時期やマナーって?
お中元は、先方が住む地域によって贈るタイミングに違いがあります。関東と関西に大きく分けられるのですが、関東の場合には「7月初旬から15日まで」、
関西の場合には「8月初旬から15日まで」となっています。
このほかにも、知っておきたいお中元のマナーには、こんなことがあります。
●基本的には手渡し
最近では、県外だけでなく県内であっても引き受けてくれる郵送サービスもあるため、
こうした郵送サービスを利用する人も増えています。
ですが、中元とは本来「日頃の感謝とこれからも変わらぬ付き合いをお願いする」
というのが目的にあります。
ですから、直接中元をもって挨拶をするというのがマナーになります。
●喪中でもお中元は関係ない
日頃の感謝の気持ちを伝えるのが中元の意味にありますから、
喪中であっても、基本的には関係ありません。
ただし、喪中の場合は、不幸から日が浅いこともありますから、
贈る側にも受け取る側にも配慮が必要です。
■喪中の相手に贈る場合
中元ではなく、「暑中御伺」や「忌中御見舞」などが良いでしょう。
■贈る側が喪中の場合
無地熨斗にすると、無難です。熨斗を付ける場合は、「暑中御伺」などが良いでしょう。
お中元の送り状って?
お中元の基本は手渡しであるため、品物を贈るだけでは、受け取る側の印象としてはあまりよくありません。
最近では、デパートからの直接発送が主流なので見落としがちなのですが、
こういう場合も、本来は手紙やメッセージを添えるのが基本にあります。
品物と同封できない場合は、葉書で別に郵送するのが一般的です。
目上の方や改まった相手の場合は、葉書では失礼になりますので、手紙を準備します。
●送り状のポイント
送り状で書く内容は、3つです。
①時候の挨拶
基本は、「拝啓で始まり敬具で締める」の形式をとります。
【例】
拝啓 向暑の候 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 ~ 敬具
②日頃のお礼
中元の本来の目的にあたります。
【例】
「平素より妻ともども大変お世話になり、本当に有難うございます。」
「日頃は何かとお世話になり、有難うございます。」
③品物の内容
「感謝の気持ちを込めた品物を贈らせていただきました」という内容を、
書き添えることが大切です。
一般的には、「心ばかりの品を送りましたのでお納めください」と記します。
スポンサーリンク
お中元のお礼状
お中元をいただいたら、お礼をするというのもお中元のマナーです。そのため、お礼状を準備しますが、お中元のお礼状には4つのポイントがあります。
①礼状を出すタイミング
お中元の礼状は、お中元が届いてから3日以内に投函するのがマナーです。
取り急ぎ電話にて御礼をする場合もありますが、その場合も、
電話だけでなく礼状をお出しするのがマナーです。
②葉書ではなく封書で
葉書は「端書」とも表現されるように、簡略的な印象が強いものです。
ですから、基本的には封書で礼状を出すのがマナーとされています。
特に、目上の方に対して葉書で礼状をだすのは失礼にあたります。
③お中元のお礼と日ごろの感謝の言葉をいれる
返礼品を準備する必要はありませんが、日頃のお礼をすることは大切です。
【例】
「この度はお心のこもったお品を頂戴し、誠に有難うございます。」
「本日はお心のこもったお品をいただき、誠にありがとうございます。」
「いつもながらのお心遣い心より感謝申し上げます。」
④相手の健康や息災を願う言葉を入れる
「今後も継続したお付き合いをさせていただく」という前提が中元にはありますので、
相手の健康を願う言葉を文中に入れるのが基本です。
まとめ
初めてのお中元も、お中元に関するマナーさえわかっていれば、難しいことはありません。日頃の感謝の気持ちを込めて、メッセージを添えて品物を送れば、
相手の印象もよくなります。
今回のまとめを参考に、中元デビューを成功させてくださいね。









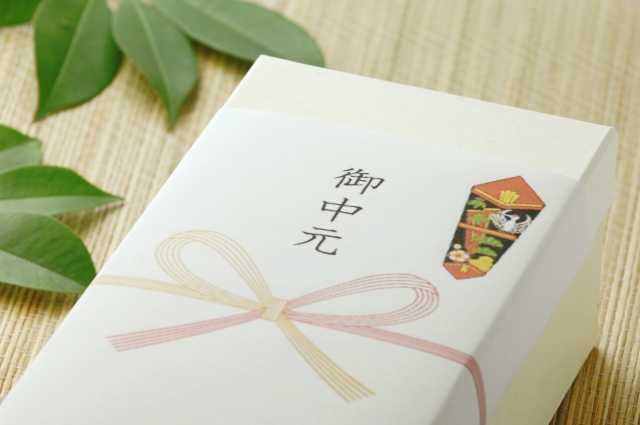

コメント